■欲求ではなく必要の充足■~公的サービスの顧客とは~
公的機関が成果をあげる上で必要なものは、”仕組み”であり、
その適用には、公的機関を次の三種類に分けて考える必要がある。
種類2【予算から支払いを受ける公的機関】
典型として公立の学校や病院がある。
組織は公的機関が所有して、運営は競争状態に置くというサービス機関だ。
これらの公的機関の収入は、予算として、国を通して国民から支払われるが、
国民は公的機関にとって本当の意味での顧客ではない。
国民は望むと望まざるとにかかわらず、税金、保険料などの形で
強制的に支払いをさせられている。
一方サービスを受けるのは生徒や患者であり、彼らは顧客である。
しかし、顧客は否が応でもサービスを受けざるを得ない。
顧客の欲求から生み出されるサービスではなく、誰もが持つ必要性から
生み出されているのだ。
ドラッカーは、このような特性を持つサービス機関には、成果について
最低限の基準を設けると共に、競争が必要であるとする。
しかも顧客は、複数のサービス機関から選択できることが望ましいとする。
「この種のサービス機関が生み出すものは、欲求の充足ではない。
必要の充足である。
学校や企業内サービス部門は、誰もが持つべきもの、
持たなければならないものを供給する。」
~P.F.ドラッカー「マネジメント」
私のランクは?


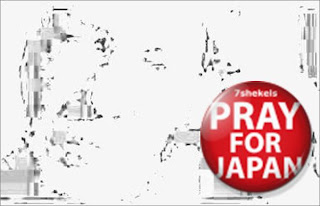


コメント