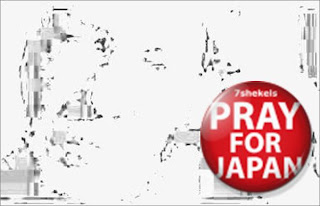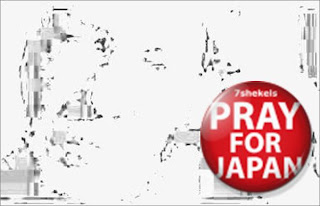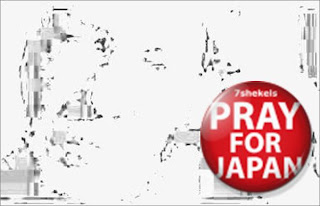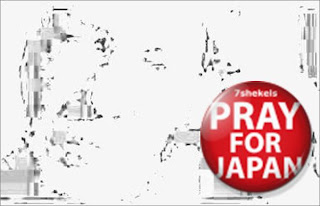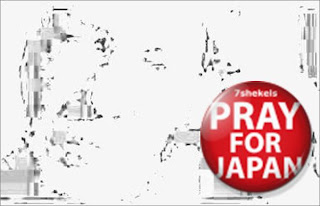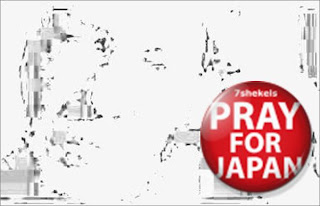続いてドラッカーは、組織構造の種類について述べる。 マネジメントの側面から見て次のとおり分類する。 【仕事中心の組織構造】 ◆職能別組織 営業部、総務部等の機能別・段階別に分割したいわゆる縦割り型組織を指す。 この組織は、自らの組織上の立ち位置が明確に理解でき、 自部門の目標も明確になるというメリットがある。 逆に、組織全体の目標が見えにくく組織の目標と自分の目標を 関連付けにくくなるというデメリットがある。 この組織構造は、単一のサービスや製品を作り出す比較的単純な工程を持つ企業に向いている。 複雑な作業が不可欠な組織には、不向きである。 ◆チーム型組織 組織内の専門分野からメンバーを集めて特定の課題に対して、チームで取り組む形態を指す。 タスク・フォース、フロジェクト・チームなどが該当する。 この組織には明確に規定された目標が必須で、デメリットとして、 意思疎通に費やす時間が長くなる傾向にあり、人数か多くなると機能維持が困難になる。 【成果中心の組織構造】 ◆分権組織 この組織は、自立的な事業体から編成され、事業部制や社内企業制などを指す。 一般的には、事業体内部に職能型組織を職能別組織を持つ。 そして、個々にマネジメント機能を所有し、自立的に事業体を運営する。 事業体が自主的に運営されるので、メンバーは事業体の目標と自分自身の目標を把握しやすくなり、 コミュニケーションや意図決定も円滑に進むこととなる。 ◆擬似分権組織 規模が大き過ぎて職能別組織では効率的に機能しない場合に採用する形態である。 【諸々の関係中心の組織構造】 ◆システム型組織 多様な価値観や変化を統合できる形態だが、明快性や経済性に欠ける。 【意思決定中心の組織構造】 ◆この組織構造は未だ開発されていないが、 ドラッカーは、これが実用化されれば、 その影響はきわめて大きなものとなると期待する。 「マネジメントには、仕事、成果、関係のほかに意思決定という側面がある。 今日のところ、この意思決定中心の組織構造は開発されていない。 可能性の域を出ない。 だが、これが実用に供しうる形で開発されるな...